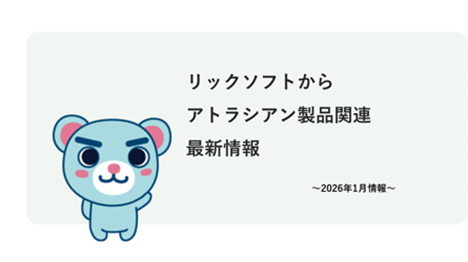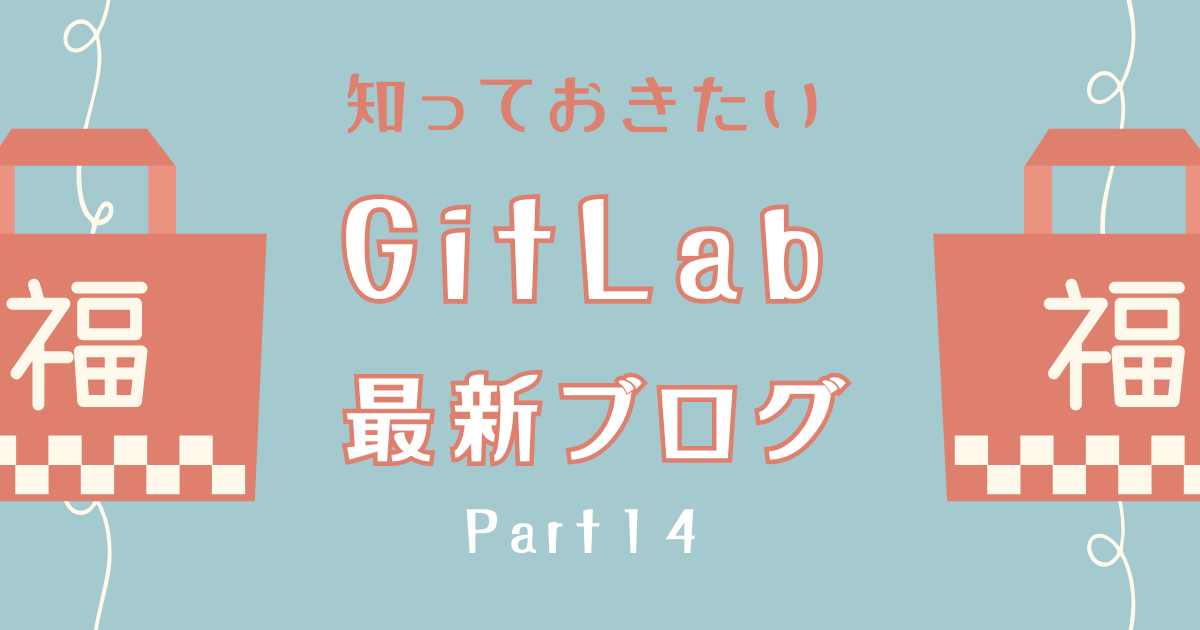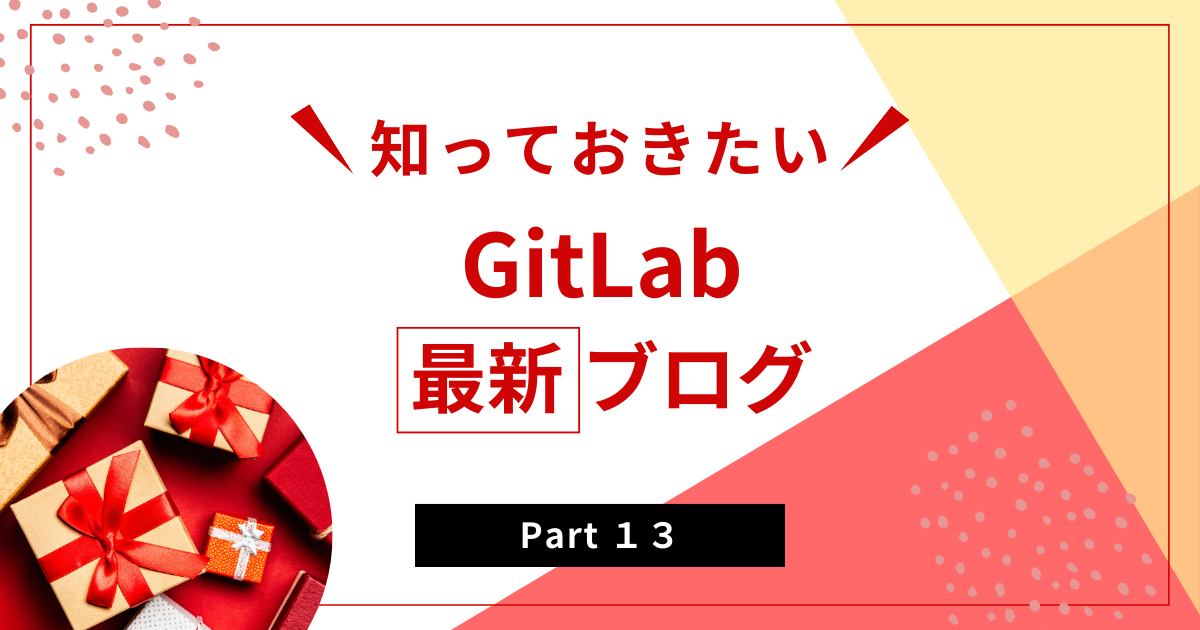【イベントレポート】開発生産性Conference2025

皆さんこんにちは。
SB C&Sの近藤です。
先日開催されました「開発生産性Conference2025」のイベントレポートになります。この記事では、2日目に行われたセッションのご紹介と感想を書かせていただきます。
※イベントスケジュールはこちら

イベント概要
開発生産性Conference 2025は、エンジニアリング組織の生産性向上に関する最新の知見やベストプラクティスを共有する、日本最大級のカンファレンスです。国内外の有識者や企業が一堂に会し、開発生産性の向上に向けた取り組みや事例が紹介されました。
開催情報
- 日程:2025年7月3日(木)・4日(金) 9:30〜19:00
- 会場:JPタワーホール&カンファレンス(東京・丸の内)+オンライン配信(ハイブリッド開催)
- 主催:ファインディ株式会社
- 参加費:無料(事前登録制)
- 参加対象:エンジニア、マネージャー、経営層、開発生産性に関心のある方
- 参加規模:2,000名以上が参加登録。大企業からスタートアップまで幅広い層が参加。
こんな方におすすめ
- 複数の開発チームをマネジメントしている方
- 開発組織のトップや意思決定層
- 日々の業務で開発生産性向上に取り組んでいる方
- 最新の開発生産性トレンドや事例を知りたい方

開発を止めないセキュリティ体制
-Visional流 DevSecOps 横断改革-
ビジョナル株式会社の峯川様と、株式会社アシュアードの鈴木様による「開発を止めないセキュリティ体制 -Visional流 DevSecOps 横断改革」と題した講演が行われました。本記事では、その講演内容をもとに、ビジョナルグループが実践する「開発を止めないセキュリティ」の全体像と具体的な取り組みについてご紹介されました。
ビジョナルグループの概要とミッション
ビジョナル株式会社は、HRテック、M&A、物流、サイバーセキュリティなど多岐にわたる事業を展開する企業です。2020年2月、株式会社ビズリーチがグループ経営体制に移行したことをきっかけに設立されました。グループミッションは「新しい可能性を次々と」。社会の課題を発見し、事業を通じて解決、業界の仕組みを変革することを目指しています。
セキュリティ室の体制と役割
- マネジメントチーム:セキュリティルールの策定やプライバシー法令対応など、ガバナンスを担当。
- オペレーションチーム:日々の監視や脆弱性診断、インシデント対応など、現場の安全を守る役割。
- アーキテクトチーム:将来の脅威を見据えた技術戦略の立案・導入を担当。
この3チームが連携し、グループ全体のセキュリティを支えています。
グループ横断の支援
14名のセキュリティ室メンバーが、10を超えるプロダクトと30以上の社内システムのセキュリティを一括して担保。独立した専門組織として、ビジネスの成長を安全な基盤で支える体制を構築しています。
多様性を活かすセキュリティ方針
ビジョナルグループには、事業フェーズ、開発文化、リリースサイクルが異なる多様なチームが存在します。画一的なルールの押し付けではなく、各チームと対話しながら納得感のあるリスク評価や柔軟な支援体制を重視しています。
セキュリティは事業のブロッカーではなく、開発を加速させるパートナーであるべきという思想が根底にあります。
開発を止めないセキュリティの具体策
- 明確なセキュリティ基準の策定
- アプリケーション脆弱性だけでなく、クラウド環境や開発プロセス全体を管理対象に含める。
- 企画や設計段階からセキュリティ評価を実施し、後工程での手戻りを防止。
- 設計段階でのセキュリティレビュー
- 実装前の設計段階で、アーキテクチャ図などを基にリスクを洗い出し。
- 開発チームと対話形式で課題を明確化し、認識のズレを防止。
- 内製化による脆弱性診断の効率化
- 外部委託によるリードタイムや調整コストを削減し、スピーディーな診断を実現。
- 申請フォームから依頼→自動でチケット発行→進捗管理を一元化。
- 開発チームのリリーススケジュールを最優先に柔軟対応。
- セキュリティチェックシートの運用
- 年1回、プロダクトごとに約80項目のチェックシートで健康診断を実施。
- 設計・運用プロセスの実効性も確認し、弱点を可視化。
- ダッシュボードやレーダーチャートで全体状況をリアルタイム分析。
- 継続的な脆弱性スキャンとリスク統一評価
- 各種スキャンツールの結果を統合分析基盤で一元管理。
- 全ツールのリスクレベルをビジョナル独自基準で再評価し、優先度を明確化。
その他のセキュリティ施策
- リスク判定ロジックのチューニング:環境情報(本番/検証、インターネット接続可否など)を加味してリスク評価を最適化。
- 監視チームとの連携:修正が間に合わない場合は仮想パッチ等で一時的に防御。
- 脆弱性情報の自動収集:情報を集約し、影響のあるチームに迅速通知。
実際の現場の声と変化
- セキュリティルールや評価基準は、現場との対話や草の根活動によって徐々に浸透。
- 内製化による脆弱性診断は、依頼からレポートまで最短1週間、通常2週間前依頼で十分対応可能。
- セキュリティチェックシートの点数化により、グループ内での比較・改善が促進され、全体のレベルアップに寄与。
- プロダクトの成長フェーズに応じて、チェックシート項目も柔軟に調整。
まとめ
「最高の速度は最高の安全から生まれる」という信念のもと、ルールで縛るのではなく、開発者を信頼し、挑戦を支えるパートナーとして活動しており、これからも新しい可能性を生み出す挑戦を、盤石なセキュリティ基盤で支えていく必要があることがわかる事例と説明があり、普段セキュリティを担当していない方にもセキュリティ対策のイメージがわかりやすい内容だっと思いました。
コードのその先へ:開発者体験を活性化させる方法
NetflixのエンジニアリングマネージャーであるKate Wardin様による「コードのその先へ:開発者体験を活性化させる方法」に関する講演内容をもとに、ソフトウェア開発現場で本当に価値ある生産性とは何か、そして持続可能なハイパフォーマンスチームを実現するためのカルチャーや指標、リーダーシップのあり方についてご紹介されました。
生産性のパラドックス:何を測るかが行動を決める
- 「測定」そのものがインセンティブを生み出す
コード行数やチケット消化数など、数値化しやすい指標だけを重視すると、チームはそれらに最適化する行動を取りがちです。 - アウトプット重視の罠
例えば、コード行数が多い=生産性が高いと誤解されがちですが、実際には複雑性やバグ、保守性の悪化を招きます。
本当に問うべきは「どれだけシステムをよくしたか」です。
意味のある指標を測る
- アクティビティ≠生産性
ストーリーポイントをたくさんクローズしても、必ずしも価値あるデリバリーやチームの幸福度には結びつきません。 - 見えない貢献の重要性
複雑な問題解決やコラボレーション、メンターシップ、技術的負債への対応など、数値化しづらいが重要な活動も評価対象に含めるべきです。
持続可能な生産性に必要な6つの要素
- 強力なコラボレーション
- チーム間・部門間の連携、知識共有、明確な役割分担
- 事前検証による継続的改善
- 効果的なコミュニケーションと連携
- 透明性ある進捗管理、前提の明示化、スマートな意思決定
- 無駄な会議の排除、明確なアジェンダと合意形成
- フォーカスタイムの確保
- 集中作業時間(ディープワーク)の確保
- ミーティングの最小化、タスクのバッチ処理、認知負荷の軽減
- 適切なツールとワークフロー
- 本当に役立つツールだけを選定し、不要なものは排除
- チームの文脈に合ったKPIの選択
- 心理的安全性
- 否定的な結果を恐れず発言できる環境
- フィードバックを歓迎し、失敗から学ぶ文化
- 4象限モデルで「学習ゾーン」を目指す(高い安全性×高い基準)
- 成長と進歩
- クリアなキャリアパスと成長機会の提供
- ハッカソンやイノベーションウィーク、メンターシップによる学びの促進
- 失敗を学びの機会と捉えるマインドセット
Netflixでの開発生産性指標
- ディープワーク(集中作業時間)
エンジニアへのサーベイで「どれだけ邪魔されずにコーディングできたか」を定性的に測定。 - マージまでの時間・PRオープンタイム
コードレビューやマージの迅速さも重視。 - 本番リリースへの自信度(コンフィデンス)
変更が本番投入できるかどうかの自信度を指標化。 - 心理的安全性スコア
Googleの5つの質問を用いたサーベイで、チームの心理的安全性を定期的に測定。 - デプロイ頻度
プロダクトのリリースサイクルの速さも重要な指標。
Netflix流・心理的安全性と高基準の両立
- ドリームチームの現実
Netflixでは高い基準と強力なフィードバック文化が根付いており、パフォーマンスが著しく低い場合は解雇も珍しくありません。 - それでも心理的安全性は保たれる
上司や同僚からのフィードバックが日常的に行われ、失敗は学びのチャンスとして受け入れられています。
重要なのは「個人よりもまず会社のために考える」ことと、深い信頼関係の構築です。
リーダーシップとカルチャー変革のポイント
- 何を測り、何に報酬を与えるかを見直す
- 成果を重視し、アウトプットや可視性だけに最適化しない。
- 開発者体験(DX)とビジネス成果の連動
- DX向上はデリバリーの高速化や離職率低下、競争優位にも直結。
- リーダーが示すべき姿勢
- 障壁や摩擦の解消に目を向ける
- チームの健全性や心理的安全性を重視
- コラボレーションや知識共有を奨励
- 非現実的なタイムラインにはノーと言う
- 質の高い仕事や堅牢なシステムを称賛
まとめ
Netflixの開発現場では、単なるアウトプット指標ではなく、コラボレーション・コミュニケーション・フォーカス・ツール・心理的安全性・成長という6つの要素を重視し、持続可能なハイパフォーマンスチームづくりを実践しています。
リーダーは、測定指標や評価制度、カルチャーの方向性を見直し、個々の成長とチームの健全性、そしてビジネス成果をつなげる役割を担っています。
開発者体験の向上は、組織の競争力を高める最重要テーマであり、まずは「何を測り、何に価値を置くか」から見直すことが重要であることを重要であることや、業務への取り組むマインドとしても参考になることが多く、とても学びがありました。
約3万チームの「Findy Team+」統計データから見る、開発生産性の今と未来
ファインディ株式会社の稲葉様より「約3万チームのFindy Team+の統計データから見る開発生産性の今と未来」と題した講演が行われました。
ファインディ株式会社が蓄積した膨大なデータから見えてきた開発現場のリアルと、生成AI時代における開発生産性の変化についてご紹介されました。
Findy Team+とは
- 開発現場と経営をつなぐSaaSツール
- GitHubやJira、Backlogなどのデータを連携し、開発パフォーマンスを可視化・AI分析・改善提案
- チームメンバーの貢献度や施策の効果検証もグラフィカルに可視化
- 導入実績
- 2021年ローンチ、4年で3万5,000チーム超が利用
- 大手からベンチャーまで幅広い開発組織が活用
- 日本だけでなくインド・韓国にも展開、グローバル利用が拡大中
国・文化による開発生産性のアプローチの違い
- 日本:マネジメントも現場もボトムアップ志向、質とスピードのバランスや定性観点を重視
- インド:トップダウン・個人主義寄り、スピードや短期成果を重視
- 韓国:クローズドな傾向、データは経営層のみが把握
データで見る開発生産性の今
チーム構成・開発手法別の傾向
- 少人数×スクラム開発のチームが最もアウトプット量が多い
- ブランチ戦略では「トランクベース×少人数」が高アウトプット
- GitflowとGitHub Flowの差は意外と小さい
ビジネスモデル別の傾向
- BtoC企業の方がBtoB企業よりアウトプット量が多い傾向
- 受託開発は、特に少人数・アジャイル型で高いアウトプット
生成AI活用のインパクト
- GitHub Copilot利用企業は非利用企業の約1.6倍のアウトプット
- Claude Codeなど後発AIツールも急速にシェア拡大
- AIツールの「必須導入」企業が4割近く、推奨も含めると過半数超
- 主なユースケースは「コード生成・保管」「テストコード生成」「コードレビュー・品質チェック」
- 上流工程(要件定義・ユーザーストーリー等)での活用はまだ3割未満
生成AI活用の評価と課題
- 効果評価方法
- 定量(リードタイム・アウトプット量)+定性(アンケート・満足度調査)の両面で実施
- 体感効果
- 約9割の組織が「アウトプットスピードが改善した」と実感
- ただし、事業指標やプロダクト指標の改善は2割弱にとどまる
- 開発者満足度や効率も9割が改善を実感
- 一方で「AI疲れ」「業務ストレスの増加」も一部で顕在化
生成AI時代の開発生産性:変わること・変わらないこと・変えるべきこと
変わること
- ボトルネックの変化
- 実装工数から、テスト・要件定義など未AI化領域へシフト
- バリューストリーム全体の見直しが必要
- ロール&レスポンシビリティの再定義
- 役割の境界が曖昧に。全員がプロダクトオーナー的な意識を持つチームづくりへ
- 少人数・高速開発の事例も増加
変わらないこと
- コンテキスト共有の重要性
- 意思決定や成果物のドキュメント化、共通フォーマット運用、情報の集約
- GitHub等での一元管理や、誰でも参照できる状態づくりが鍵
- 開発のゴール=投下資源に対するアウトカム最大化
- 開発スピード・デリバリー最適化・仮説検証回数の最大化
変えるべきこと
- 「満足度」から「効力感」重視へ
- ユーザーの期待に応えている実感(効力感)が低い現状
- 全員が当事者意識を持ち、成果にコミットする体制へ
- 専門性の壁を越えた「全員プロダクトオーナー」の意識改革
ファインディの新たなアプローチと今後
- デリバリー領域
- AI活用状況の可視化(YDIプラス)
- バリューストリームごとのリードタイム・ボトルネックの可視化
- プロジェクト単位の成果振り返り機能
- AIによる課題発見・改善提案
- 「AI疲れ」対策のための開発者向けサーベイ
- ディスカバリー領域
- コンテキストマネジメントを重視した新プロダクトを開発中
- 暗黙知の形式知化、データ集約・AI活用・モデルアップデートのサイクル
- ターゲット設計・課題仮説設計・優先度設計・仕様化まで一気通貫で支援
- エンジニアがより顧客価値創出の中心となる時代へ
まとめ
- 生成AIの浸透で開発現場のボトルネックや役割分担が激変
- 変わらず重要なのは「コンテキスト共有」と「アウトカム最大化」
- これからは「開発者の効力感」と「全員PO意識」で成果を追求
- ファインディはデリバリーからディスカバリーまで、AI・データを活用した新しい開発生産性支援に挑戦
開発者が自らの手で価値を届ける時代となり、ファインディ社は、そんな現場を支えるパートナーとして、これからも進化していきたい決意がわかる講演でした。
生成A Iを利用する企業とそうでない企業とでは、アウトプット量に大きな差が出てきており、今後成長を目指すためには生成AIの利活用は必須項目であることをご紹介されました。
私も普段からAIを積極的に取り組んでいるつもりではいますが、もっと効率化できる業務もあると思うので見直したいと思いました。
エンタープライズの壁を破るプラットフォームエンジニアリング:「セキュリティ統制」「開発生産性」の両立
株式会社エーピーコミュニケーションズの上林様と、株式会社NYK Business Systems(NBS)の赤坂様が、「エンタープライズの壁を破るプラットフォームエンジニアリング:「セキュリティ統制」「開発生産性」の両立」というテーマで、多くのエンタープライズが抱える「セキュリティ強靭化」と「開発生産性」のジレンマについて事例を交えてご紹介いただきました。
NBSのクラウド活用と開発生産性向上の取り組み
NBS(NYKビジネスシステムズ)とは
- 日本郵船グループのIT子会社として1988年に設立。
- 社員数156名、東京・ニュージャージー・ロンドン・シンガポールに拠点。
- グループ内のITインフラ・クラウド基盤の企画運営、セキュリティガバナンス強化などを担う。
社内開発者へのヒアリング結果
- 開発者の満足度は平均6.0(10点満点)。
- 「標準が少なく無駄な作業が多い」「インフラ部門への依頼が必要で進まない業務がある」「自動化・標準化を進めたい」などの声が上がった。
- クラウド環境の申請・構築プロセスが煩雑で、効率化を望む意見が目立った。
セキュリティコントロールの進化
- 従来は「ゲート型」セキュリティ(申請・許可制でリードタイム発生)。
- 今後は「ガードレール型」セキュリティへ移行。
- 予防的ガードレール:リスクある操作を禁止
- 発見的ガードレール:逸脱やガイドライン違反を検知
自由と統制のバランス
- 両パターンのニーズに応じて「選択可能なクラウドマンション」を提供。
- セルフサービスと自動化を推進し、セキュリティ・ガバナンスを強化しつつ、開発者の負担を減らす取り組みを進行中。
プラットフォームエンジニアリングによる課題解決
エンタープライズ企業の課題
- 品質管理やセキュリティ管理など、複数部門をまたぐ承認・申請フローが存在。
- クラウド環境の申請から運用開始まで最大3ヶ月かかることも。
- 待ち時間の長さから、開発チームが独自にクラウドを使い始め、ガバナンスが効かなくなるリスクも。
プラットフォームエンジニアリングとは
- 開発者が外部部門へ依頼せず、プラットフォームを通じてセルフサービスで環境構築やデプロイができる仕組み。
- ガバナンス(統制)とアジリティ(俊敏性)の両立を実現。
推進方法とツール
- 開発者ポータル「Backstage」を活用。
- ソフトウェアテンプレートやカタログ機能、200以上のDevOpsツールと連携可能。
- セルフサービス化・資産の見える化・組織展開を促進。
- 成熟度モデルによる3ステップ展開
- 少人数でスモールスタート(MVP構築)
- 社内コミュニティ的に横展開
- 全社標準化
効果検証事例
- 申請から運用開始まで最大90日→10日に短縮。
- ROI算出では、30名規模で数千万円レベルの改善効果も。
- Backstageを使ったGitOpsセルフサービス化で、2週間→数十分に短縮。
- ガバナンスとアジリティの両立が実現。
まとめ
NBS社が推進するクラウド基盤のセルフサービス化と自動化の取り組みは、開発者体験の向上と生産性アップに非常に効果的であると感じました。特に、エンタープライズ特有の承認フローやガバナンスといった複雑な課題を、プラットフォームエンジニアリングの考え方やツールを活用して乗り越えている事例が増えている点が印象的でした。現場のリアルな課題や具体的な取り組みが紹介されており学びのある講演でした。
開発生産性を測る前にやるべきこと:組織改善の実践
株式会社カオナビの富所様が「開発生産性を測る前にやるべきこと 組織改革の改善の実践」と題して講演されました。
カオナビとは?会社紹介と事業概要
- カオナビはタレントマネジメントシステムを提供する企業。社員の顔と情報を一元管理し、人事戦略や評価、社内コミュニケーションを支援します。
- 創業は2012年。現在は「労務メート」「ヨジテック」など複数プロダクトを展開するマルチプロダクト戦略を採用。
- ステートメントは「性別・学歴・肩書きはラベルにすぎない。働くにテクノロジーを実装し、社会を変える」。
柔軟な働き方と組織の特徴
- ハイブリッド勤務(リモート・出社自由)、スイッチワーク、家庭や介護への柔軟対応など、多様な働き方を実現。
- CTO室はプロダクト開発部門と横並びの独立組織で、全社横断で技術課題の解決や技術広報を担う"なんでも屋"。
組織改善の歴史とフェーズ
創業〜急成長期
- 2012年 サービス開始:100%外注開発・顧客ごとの個別カスタマイズでスタート。
- 2015年 リプレイスPJ発足:個別対応の限界からマルチテナントSaaS化へ転換。
- 2017年 職能別組織導入:企画・開発・QAの職能別組織化でスケールし、利用企業数1000社突破。
「大改善時代」とその課題
- 急成長の裏でセクショナリズム(派閥意識)やコミュニケーション不全、開発スピードの鈍化が深刻化。
- 職能間の壁が厚くなり、仕様変更やリリースの柔軟性が失われ、ビッグバンマージによるリリース失敗も多発。
- 「社内受託開発」のような受け身体質や、エンジニアの神聖化も発生。
クロスファンクショナルチームへの転換
- 2019年以降:部門横断の選抜チーム(クロスファンクショナルチーム)を導入。企画・開発・QAが一体化したチーム体制へ。
- 2023年には利用企業数4000社を突破し、組織改革の成果が数字にも表れる。
改善のきっかけと方針
- 背景には「面白くなかった」「顧客に良いものを届けられない」という現場の空気感があった。
- 数字や指標で判断したのではなく、「変化に適応しやすい体制」「楽しい現場」への自然な連鎖反応として改革が進行。
- 生産性を"上げる"より「改善しながら生産性を下げない」ことを意識。
カオナビの具体的な組織改善施策
横断コミュニケーションの強化
- オアシス:オープンスペーステクノロジー形式の社内交流会。部署・職種を超えて月1開催、リモート参加も可能。
- アジャイルオープンドア:テーマを募り、リモートで自由に議論できる場。
- カジュアル交流イベントや全社スプリントレビュー:営業やカスタマーサクセスともつながる機会を創出。
技術・情報共有の仕組み
- アーキテクチャディシジョンレコード(ADR):町の掲示板のように設計や改善案を全社に共有し、透明性を確保。
- 設計レビュー/相談会:Slackワークフローで誰でも気軽に相談できる場を用意。
- 社内勉強会(寺子屋・語り場など):隔週開催で登壇希望者が絶えない活発な文化。
- YouTubeライブ配信:社内外向けに技術発信、アーカイブも活用。
中長期課題への取り組み
- CTO室頼り:月1回、サービス改善のヒントとなる指標を健康診断的に発信。
- カモベンツ:中長期課題に取り組む有志集団。
- 考える会:バックエンド・フロントエンドなど分野ごとに自由議論。
採用・教育・社外発信
- 社内外勉強会やカンファレンス参加、書籍購入制度など、学びと発信の機会を幅広く提供。
- アルゴス(チーム成長サイクル支援):チームごとの成長や横断交流を促進。
組織改善のリアルと成果
- 改善活動は「愚直な積み重ね」。即効性のある処方箋はなく、地道な取り組みが6年かかってようやく成果として現れる。
- チーム間コミュニケーションの改善や、価値提供スピードの向上、技術的負債の解消など、目に見える効果が出てきた。
- 開発生産性指標(Four Keys等)は、安定したチーム体制ができてから"健康診断"として活用し始めている。
まとめ
カオナビの組織改革は「楽しく、愚直に、みんなで変えていく」ことが原動力で、数値管理や指標も大切だが、まずは現場の課題を直視し、地道な改善を積み重ねることが最重要としている。
組織改善に「銀の弾丸」はなく、現場の声・文化・小さな工夫の積み重ねが大きな変化を生むことが多い。些細なことにも目を凝らしていくことが大切だと感じる講演でした。
最後に
開発生産性Conference2025では、最新技術情報をはじめ、各社企業の取り組みや事例、組織作りまで。エンジニア、営業、経営に関わるすべての人に向けて、幅広く参考になる情報を得ることができるイベントでした。ブースなどでは直接ベンダーの方ともコミュニケーションをとることができ、各社の取り組みと合わせて、製品やサービスの理解を深める機会となりました。

この記事の著者:近藤泰介 -Taisuke Kondoh-
SB C&S株式会社
主にデジタルワークスペース実現のためのソリューション展開、案件支援、先進事例の獲得、協働パートナーの立ち上げを経験。
現在は新規事業開発やDevOps・クラウドネイティブに関する提案活動、販売代理店の立ち上げ、
国内外の新規商材発掘(目利き)/調査といったTec Scouting活動に従事。
また、Microsoftを中心としたビジネス領域の調査・プリセールスも行う。

DevOps Hubのアカウントをフォローして
更新情報を受け取る
-
Like on Facebook
-
Like on Feedly